10月の行事食
栗ご飯、芋ごはん(十五夜・十三夜)
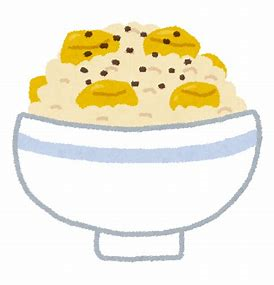
毎年、9月か10月に十三夜と十五夜の日があります。(その年によって変動アリ)
十三夜は別名「栗名月」と言われます。そして十五夜は別名「芋名月」と言われます。この両方の月見を行うことが、縁起が良いとされています。
栗ご飯も芋ごはんも、それぞれの材料と共に塩を入れて炊くととてもおいしいですね。余計な調味料は不要です。
11月の行事食
千歳あめ(七五三)

千歳あめの原料は餅米と麦芽です。これらを煮詰めて溶かし、棒状に伸ばして冷やし固めます。長い千歳あめを食べることによって、(千歳まで)長く生きられるようにという願いが込められています。ですが、長ければいいというものでもなく、
- 太さ15㎜
- 長さ1m以下
という決まりがあります。
1mの千歳あめって…。そんな長いあめは食べるのも一苦労ですね(笑)
ですが、千歳あめを切ったり折ったりしてはいけないというルールはありませんので、食べられるサイズに切って食べることをお勧めします(^_^)
赤飯(七五三)
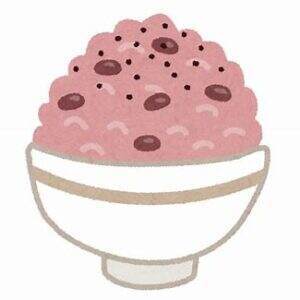
七五三に限らずお祝い事でよく食べられているご飯ですね。
もち米と米(2:1)を使用して30分ほど下茹でした小豆と一緒に炊き込んで作ります。もち米を使用しているのでモチモチの食感が楽しめますね。
でも、私は子どものころ赤飯が嫌いでした(笑)大人になった今では食べることもできますし、どちらかと言えば好きな食べ物になりました。
子どもの頃は、粒あんが嫌いだったのでおそらく赤飯も嫌いだったのだと思います(;^_^A
12月の行事食
かぼちゃの小豆煮(冬至)

元々は運盛りで「ん」のつく食べ物を食べると運気が上がるとされてきました。
- なんきん(かぼちゃ)
- にんじん
- レンコン
- 銀杏
- きんかん
- 寒天
- うんどん(うどん)
これらの中から「なんきん(かぼちゃ)」が、当時に食べるものとして定着し、有名になりました。
「かぼちゃを食べると風邪をひかない」とよく言われていますが、これは体内でビタミンAに変わるβカロテンを豊富に含んでいるからなのです。ビタミンAの働きによって粘膜や皮膚の抵抗力を高めます。
また、小豆には疲労を回復するビタミンB1皮膚を丈夫にするビタミンB2、B6がとても多いのです。
一緒に煮ることによって、お互いの良いところがプラスされ、冬場を元気に乗り切る身体を作ることができるとされています。
年越しそば(大晦日)

そばはほかの麺類よりも切れやすいことから、今年一年の災厄を断ち切るという意味で大みそかの晩に食べるとされています。
讃岐うどんで有名な香川では、「太く、コシのある人生を」ということでうどんを食べる家庭も多く存在します。
一方、沖縄では「年越しソーキそば」を年越しそばとして食べる家庭が多いそうです。
ですので、そばアレルギーの方はうどんやソーキそば、そうめん、ラーメンなどで代用しても良いと思います。
晩御飯はちょっと豪勢にして、夜食にそばを食べるという人もいるかもしれませんね。



コメント