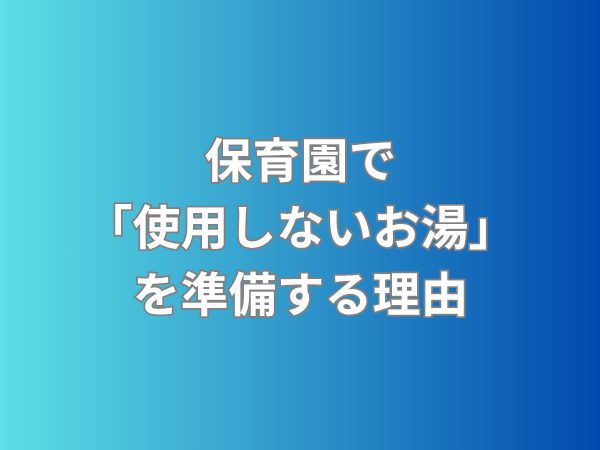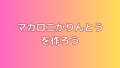私たち給食調理員には「お湯を沸かす」という仕事があります。
今回記事内で挙げる「お湯」とは、その日に飲むお湯ではありません。毎日熱々のお湯を沸かしていますが、開園からそのお湯を使用したことはありません。
さて、このお湯の意味とは…?
なぜ毎日「お湯」が必要なのか?
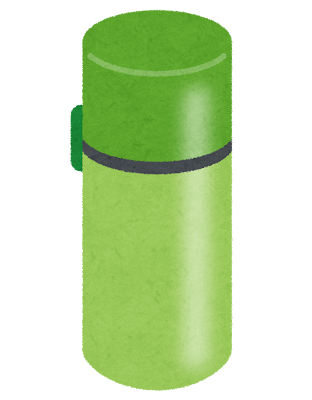
私の勤務先の園は、何十年も前からささやかれている『南海トラフ地震』が起きてしまったときに、地震の影響を大きく受ける地域にあります。
災害とは、いつ来るものか予想がつかないものです。園児が在園している時間帯に来ることも予想されます。毎日使うことのないお湯を沸かす理由は、「災害時などの緊急時に使用するお湯をあらかじめ準備しておく」ことなのです。
災害時には、停電になったりガスも止まってしまうことも考えられます。
そうなってしまうと園内ではお湯を沸かすことができなくなってしまいます。
幼い子を多く預かっている保育園では、いざというときにお湯がないと困ってしまうことがあります。
調乳

保育園は、まだミルクしか飲めないような乳児も在園います。お湯がないと乳児に「食事」を与えることができなくなってしまいます。
そうならないためにも、いつ何があっても「とりあえずのお湯」を確保しておく必要があるのです。
アルファ米の調理

お湯があれば、その他の園児用のアルファ米の調理にも使うことができます。水からでも調理ができますが、災害時であっても温かいご飯の提供は可能な限り行いたいですよね。
災害時用のお湯は何に入れているのか?
ずばり、保温効果のある水筒です。(勤務先には3本の水筒があります)
保育園では、通常業務の中でもお湯を使用することがあるので、電気ポット2台でも常にお湯を沸かして保温している状態ではありますが、水筒ですと災害時に持ち出すことが簡単です。
勤務先の保育園では、少なくとも閉園時間までお湯がある状態にします。
災害はいつ起きるかわかりませんものね。
災害時用のお湯はどこに置いておくとよいのか?
意外と悩むのが置き場所です。
空いているところならどこでも…というわけにもいかないのです。決まった場所に置いておかないと「いざ」というときに困ってしまいます。
勤務先の保育園では、事務室(いざというときに大人の手が多い場所)、0歳児の部屋(お湯を必要とする児がいる)、2階の1室(水害を想定)の3か所に置くことにしています。
地域によっては監査項目に「災害用のお湯の準備」と記されている場合も
地域差はあると思いますが、私が暮らす地域では南海トラフ地震が懸念されていますので、災害時用のお湯が準備していないと年1回ある市の監査での指摘事項となってしまいます。
指摘事項となってしまった項目に関してはすぐに改善が必要となりますので、市内どの園(認可園)にも「災害時用のお湯」は存在します。
さいごに
保育園では「いざ」というときのために子どもたちを守ることができるようにあらかじめ準備することが求められています。今回のお湯もその一つなのです。

もちろん、非常食や保存飲料水、停電やガスが止まった時に使うことのできるカセットコンロも用意してあります。
ですが、念には念を…ということで「水筒にお湯」も準備しているのです。