●日勤
●資格なしでも働くことができる
●女性が多い職場
●食事が作れれば働くことが可能
●子どもが好き
など、比較的緩い条件で募集されることの多い、「保育園の給食室」で働きたいと思っている人は、意外と多いのではないかと思います。
中でも、勤務日や時間の兼ね合いから子育て中の女性に人気があります。
さて、そんな保育園の給食室は、実際にはどのような基準で職員の募集・採用をしているのでしょうか?今回は、実際に働いている私の視点を含めた現状を書いてみたいと思います。
保育園給食現場の採用の実態

「保育園の給食室」においての正規職員の数は非常に少ない傾向にあります。
元々、採用数自体も少ない職種ではありますが、その中でも正規職員(正社員)として採用をされている人はほんの一部に過ぎないのが現状です。
小規模保育園の給食職員
2歳児クラスまでの保育をしているような小規模園では、週2~3回で日中の5~6時間の短時間パートの採用であることが非常に多くなっています。
小規模園は園児数が非常に少ない(18~40人前後)ということもあり、日々の調理業務はもちろん、発注業務、園児の食の管理、配膳・下膳の量、保護者対応…などどれをとっても幼児クラスまで持っている保育園と比べ、業務量そのものが少ないのです。
ですので多くの小規模園では給食職員は、短時間のパートで雇用することが多いのです。
幼児クラスまで保育する保育所での給食職員
保育所では、0歳児から5歳児までの多くの子どもを保育しています。
離乳食から幼児食までの作り分けも必要となり、場合によってはアレルギー食の対応もします。
保育所では、栄養士の正規職員(正社員)を1名配置するところが多く、その他は持っている資格に関係なくパートであることが多いです。
とは言っても、保育所にも規模があります。60名定員のところもあれば、300名を超える園児を見ている保育所もあります。園の規模によっても調理員の採用人数の違いがあります。
以下では、一例を書いていきたいと思います。
園児数46~150名の給食職員数
保育所の中でも比較的規模の小さめな園です。職員数は20~25名前後であることが多く、保育士などの職員も給食を食べる園では、園児+職員数が実食数となります。
このような比較的小さ目な保育園では、正規職員として栄養士を一人配置し、短時間パートを2~3人交代で勤務させている場合が多いように感じます。短時間パートは早番や遅番が存在する場合もあり、例えば午前と午後で別のパートが出勤していることもあります。
もしくは、2人の常勤を配置(うち一人は栄養士)し、休暇の交代要員として1~2名のパートを雇用している場合もあります。
この規模の保育所では、基本的には2人調理となりますが、園によっては異物混入や誤食などの事故防止の観点からプラス1名配置しているところもあります。
園児数151人以上の給食職員数
一学年に複数のクラスがあるような比較的大きめな園です。
職員数は非常勤を含めると、30名を超えるところもあります。大きめな園でも、職員が喫食する場合の食数は園児数+職員数となります。
この規模の園では正規職員を2~3名(うち一人以上は栄養士)を配置し、短時間パートを1~3名交代勤務させているところもあります。
この規模の園では基本的には3人調理となりますが、園によっては異物混入や誤食などの事故防止の観点からプラス1~2名配置しているところもあります。特に300人を超える園では常時4人で切り盛りしていることもあります。
保育園においての栄養士の役割とは

園の規模によっても「働き方」の違いがあることはおわかりいただけたと思います。
同じ栄養士であっても、小規模園の栄養士と保育所の栄養士では役割そのものの違いがある場合もあります。
小規模園の栄養士
多くの小規模園には「姉妹園」が存在します。
- 保育所の運営をしていたところが「分園」として運営している
- 母体の会社等が「複数の小規模園」を各地で運営している
- 「複数の保育所と共に複数の小規模園」も運営している
- 「これから姉妹園の開園」を検討している
などいろんなパターンがありますが、小規模園の多くは姉妹園を持っています。
小規模園であっても、「正規職員」として雇用してもらえるところでは日々の調理業務に加えて、献立作成や栄養価計算などの「栄養士業務」をさせてもらえるところもあるでしょう。
しかし、短時間パートでの採用である場合にはすでに「献立を作る人」が別に存在しているため、日々の調理業務などをおこなうための採用であると思ってた方が良いでしょう。つまり、調理員としての採用である可能性が高いということです。
この場合はまあ、栄養士としての知識が「役立つかも」くらいなものです。
小規模園のパート求人で「栄養士」と書かれていても、稼働時間のことも考えると「栄養士業務を行う時間がない」こともわかりますからね。
ですので、小規模園で「栄養士として」働きたいと思っている人は、正規職員で求人をしている園を探す方が自分のやりたい仕事が見つかる場合があります。
(園の方針にもよりますので、パート採用であっても、面接時にしっかり確認をして従事する業務を考えるという方法もあります。)
保育所の栄養士
保育所では、正規職員として栄養士を雇用しているところが多いです。
正規職員として1名採用している場合は、その栄養士に「栄養業務と給食業務のすべて」を任せていることが多く、献立作成から栄養管理、受発注から給食室のシフト作りまで様々な業務を行っています。
正規職員として2名の栄養士を雇用している場合には、業務の分担なども行うことができますが、正規雇用の1名が栄養士、1名が調理師という場合には、給食室内のこと(備品の管理や清掃等)は調理師に任せ、事務作業全般は栄養士が行うなどの完全分業制をとることもあります。
保育所では、主に正規職員の栄養士が「栄養士業務」を行うことになりますが、「短時間パートの人が栄養士資格保持者」である場合はどのような働き方になるのでしょうか?
保育所での短時間栄養士の役割
すでに「栄養士業務を行うことができる栄養士がいる」場合には、基本的には短時間栄養士は調理員としての扱いになります。
理由は、
- 勤務時間内でできる業務量に限りがある
- 園児や保護者と顔を合わす時間がほとんどない
- 毎日出勤しないため、日々の業務の流れが把握できない
勤務時間内にできる業務に限りがある
短時間で働く人は、週の出勤日数も毎日ではないことが多いです。週に2~3日、1日数時間の勤務ではできる業務量に限りがあります。
そもそも給食やおやつの提供自体が毎日のことですので、そちらを優先しておこなう必要があり、「給食の調理、洗浄、片付け、清掃」などで勤務時間が終了となるのです。(そのように採用しているのです)
つまり、もともと栄養士としてのポテンシャルというより、「調理要員」としての採用が色濃く、栄養士業務を行うことは期待できません。
園児や保護者と顔を合わすことが少ない
出勤日数が少ないことに加え、出退勤時間も登校園時間とずれる傾向にある(遅く出勤して早く帰る)ため、園児や保護者と顔を合わせたり、会話をしたりすることがほとんどないのです。
ほとんど話したことのない人に「栄養指導」をされても…。というのが保護者側の立場での意見でもあります。(私もそうでした。)
人との会話はある程度の信頼関係は必要ですので、
- 顔や名前も知っている
- あいさつも良くする
- たまに会話もする
など、ある程度の認知度はあった方が園児も保護者も安心ですね。
それには「いつもいる安心感」が一番ではないでしょうか?となれば、その役目はおのずと常勤の栄養士になるのではないでしょうか。
日々の業務の流れの把握
給食業務は毎日のことです。
しかし、毎日出勤しないのであれば出勤日ごとに1から情報を把握しないとなりません。調理業務だけならまだしも、これに栄養士業務までもが加わると、とてつもない情報量となります。
現場としては、とてもじゃないがそれは勘弁…です。
正規職員の栄養士に任せましょう。
保育園における調理師・調理員の役割とは
私の感覚で言うならば、調理師も調理員も同じ扱いであると感じます。

調理師は一応国家資格であるのに対し、無資格の人を調理員と呼んでいます。
まあ、でもやることはほぼ同じですね(笑)特に、小規模園で働くにあたっては、栄養士も調理師も調理員もほぼ横並びです。給与で多少差をつけているところもありますが、仕事内容で言えば「同じ」です。
ただ、保育所となると少し変わってきます。
保育所での調理師の役割
栄養士と共に常勤として働くことで、「食育活動」や「保護者対応」などをおこなうこともあります。
長い時間保育園にいることで、園児や保護者と会話をすることもありますし、顔や名前もしっかり覚えてもらうことができます。意外とかかわりがあるのです。
もちろん、日々の調理業務も行うのですが、調理の他にも「人とのかかわり」があるということは短時間のパート職員とは異なる部分です。
また、採用の面でも「調理師」という資格があることで「常勤」としての採用をされる可能性もあるため、ここに関しては調理員との差があるのかなとは感じます。
短時間パートとしての採用である場合は、調理要員または、調理補助としての扱いとなります。
保育所での調理員の役割
無資格でも働くことができる「保育園の給食室」ですが、園によっては「調理は不可」というところもあるかもしれません。
このような園では、「調理は一定以上の知識を持っている調理師または栄養士のみ」と決められていると考えられています。
この場合は、調理補助としての採用のため、食器の数を合わせることや、盛り付け、片付けなどが業務の中心となります。
反対に給食調理もお願いされる場合もありますが、ご飯を炊くことや汁物の調理、和え物を和える(調味はされているもの)くらいのものであることが多いのです。
中には土曜日出勤(1人調理)をお願いされることもありますので、園の方針と自分の立ち位置はしっかり確認したほうがよさそうですね。
さいごに
今回は、資格・雇用形態ごとの給食職員の立場について書いていきました。
採用される人が少ない職場なだけにひとりひとりの責任は意外と大きなものになるのですが、「自分の仕事内容に納得できない」という人も意外と少ないくないと思います。(これは栄養士さんに多いです💦)
保育園の給食は求人数が稀少です(笑)しかもその中で正規雇用をされる人はほんのひとつまみ(一握りもいない)です。実に狭き門です(-_-;)
そんな狭き門をくぐって就職された方は、ぜひ雇用形態や資格にとらわれずに、自分の職場と仕事に誇りを持っても良いと思います。
どんな仕事でも必要とされている仕事ですから(#^^#)
保育園の給食調理員の経歴は?どんな仕事をしていた人が集まっているのか?
保育園の給食職員は意外と入れ替わりが多い?新しい職員が決まりやすいが辞めていく人も多い話
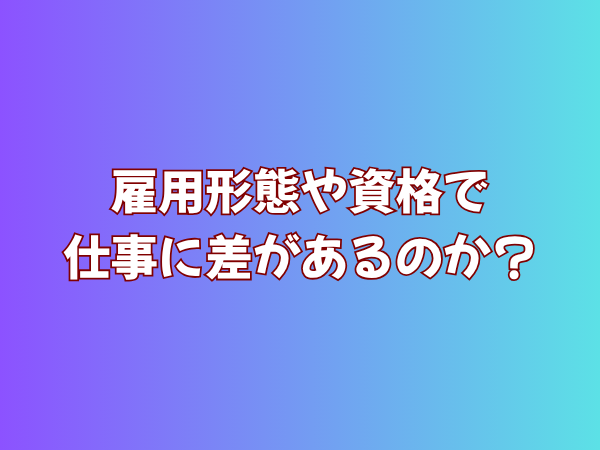
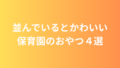

コメント